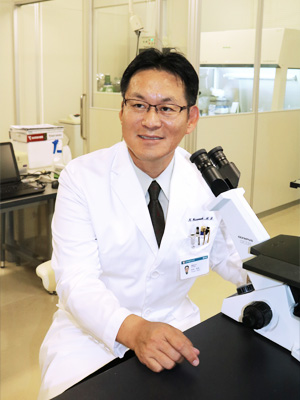研究との出会い
研究に興味を持ったのは、かれこれ30年前に遡る。
医師となって3年。結婚を機に憧れていた北陸の地「金沢」に移り住み、金沢大学大学院に進むことを決めた。それまでは、静岡(静岡県立総合病院)で外科研修医として、消化器疾患を中心にその基礎と実践をしっかりと学んだ。とくに、胃癌は年間200例を超え、多くの進行再発症例を経験し、なかでも腹膜播種(癌性腹膜炎)が診断も治療も難しいことを痛感した。
知人の紹介で、金沢大学がん研究所附属病院腫瘍外科学教室にお世話になることとなった。故磨伊正義先生が主宰する教室で、胃癌の基礎と臨床を主なテーマに活動されていた。外科治療のみならず内視鏡的診断や治療にも積極的に力を入れられている教室であったから、私自身の医師としての診療の幅が大きく広がり深さも増すことができた。また、胃癌病態の生物学的特性についても研究が進められ、膨張性発育の胃癌(分化型か低分化充実型)ならば肝転移を、びまん性発育(低分化非充実型や印環細胞癌)ならば腹膜播種を、それぞれ発症しやすいという非常に興味深い知見をいち早く発見されていた。
ちょうどその頃(1990年代)、基礎研究の分野では分子細胞生物学的研究が活発化してきていた。サイトカインの1種であるインターロイキン8を米国NIHで発見・同定した松島綱治先生が38歳の若さで金沢大学がん研究所薬理部教授として赴任された。幸運にも、大学院後半の2年あまり臨床を離れ、松島先生のもとで研究生活を送らせて頂くことになった。この経験が、医師としての私の意識を変えた。それまで、外科医には手術に関する知識と技量さえあれば十分だと思い込んでいたので、研究に対して学位取得以外に意味を見出せなかった。しかし、松島教授のもとで基礎研究を学んでいくにつれて、臨床での疑問点について基礎的側面から病態の本質に迫ることがとてもおもしろいことなのだと気づいた。
その後2年あまり一旦大学の医局に戻り、臨床の傍ら、研究を継続するため実験室整備を進めていた。科研費若手に応募し採用となったが、やむを得ない医局の人事で富山の市中病院に赴任することになり研究費は返上した。赴任した病院では、収益を上げるべく、ひたすら内視鏡治療や外科的治療に励んだ。そんなときも常に、がんの転移について“ああでもないこうでもない”と考えを巡らせていたことが懐かしい。富山赴任から5年目、病院を統括する本部から研究費公募の知らせがあった。このときとばかりに温めていた研究内容をまとめ申請すると幸いにも採用となった。
これを機に基礎研究をまた始めてみたいと一念発起し、実験転移の研究で有名な富山大学和漢薬総合研究所教授の済木育夫先生のもとを訪れた。先生は、こちらの申し出を快く受け入れて下さった。しかし、成績重視の市中病院では臨床に力を注がねばならず、研究の両立には正直限界があった。実際、臨床の合間を縫って抄読会に参加することが精一杯だった。その抄読会で、大阪大学より済木先生の教室に赴任したばかりの小泉先生とお会いすることができた。臨床面では良いこともあった。富山赴任の最終年に、病院統括本部より褒美があり、海外の学会参加を許可された。米国 ニューオリンズで開催されたAACRに初めて参加させてもらった。こんなエピソードもある。現地ホテル到着するやいなや、大使館から「ご無事でお過ごしください」との連絡をもらいあわてた記憶がある。また、米国内移動中の機内でたまたま隣に座った製薬会社の研究員の方から、「ケモカイン (CXCR4/CXCL12 axis) が実験的転移を用いた系で臓器選択性に関与するらしい」とする報告がNatureに載ったことを教えて頂いた。のちに、胃癌に応用し、済木先生ならびに小泉先生のお力を頂いて研究報告した(Cancer Res 2006)。
赴任から7年目の2002年に大学に戻ることになった。その頃医局は大きな転換期にあり、がん研究所附属病院は、金沢大学附属病院(小立野:地名)への引っ越し・統合(がん研究所附属病院はもともと離れて存在)が本決まりとなり、第1外科・第2外科・がん研腫瘍外科と、外科は3本立てとなっていた。その体制は長くは続かず、磨伊先生がご退官となるや、数年のうちに臓器別再編が一挙に進められた。医局存続をめぐり、不安や焦りを抱える日々が続いたが、そんな環境だったからこそ、現実逃避するかのように、これまで以上に研究に没頭した。
胃癌転移の臓器選択性について、とくにその予後を最も左右する癌性腹膜炎発症の機序解明と特異的な標的治療法の確立をテー マに研究を進めることを心に決めた。学位取得から10年が過ぎようとしていた頃で、とうに40歳を過ぎていた。松島先生が、東京大学に栄転された頃でもある。富山に赴任していた際、何度も「大学に戻って研究しろ」と先生より叱咤激励して頂いた。ようやく研究に集中できるようになったが、研究者としては、遅い出発となった。特別な才覚もなく器用でもない自分には、ゆっくりと自分のペースで研究を進めることが性に合っているということなのだろう。
2004年から科研費の継続的取得、癌性腹膜炎モデルの確立、研究協力して下さる方の存在(金沢医療センター;川島先生、富山大学;済木先生・小泉先生, 近畿大学;義江先生)、また2007年からがん研究所腫瘍内科の教授として徳島大学から矢野先生が赴任された。臨床を続けながら、研究結果を少しずつ蓄積し、2011年にはClin Cancer ResにHighlightsのトップに載せて頂いたのが何ともうれしかった。本研究では、悪性腹水発症に伴う癌性腹膜炎急性増悪の機序について、腹水中の増殖因子着目し、EGFRリガンドamphiregulinならびにHB-EGFの存在とそれら両増殖因子がそれぞれ前者は胃癌細胞増殖に、後者が癌間質線維芽細胞増殖に主に関与することを突きとめ、間質異常増生を特徴とする本病態のがん微小環境を理解する重要な報告となった。
癌性腹膜炎は高頻度に悪性腹水貯留を伴う。この悪性腹水貯留のメカニズムの解明に、間質線維芽細胞が産生するHGFが主に関与することを明らかにした。HGFの唯一の受容体であるMETを標的とした分子標的阻害薬投与によりマウス胃癌腹膜播種モデルを使った治療実験で腹水の治療開始からの速やかな腹水減少とともに生存期間の延長効果が確認でき、報告した(Cancer Sci 2013)。これまでに当方の研究から明らかとなった3つの重要な経路(CXCR4/CXCL12 axis, EGFR/EGFR ligands axis, MET/HGF axis)の活性化複合阻害が、単独阻害をはるかに凌ぐ抗腫瘍効果を発揮しうることを確認し、特許を出願。産学連携から医師主導あるいは企業主導の臨床試験実施を経て、病に苦しむ腹膜播種という難治な胃癌患者に何とか新たな治療薬を届けたい。
「研究する心は、その人の哲学でもある」という言葉を聞いたことがある。いつか自分の哲学となると信じ、確固たる信念を持ち、温故知新の心で臨み、協力して下さる方々に感謝して、1人でも多くの患者さんを救えるような発見を目標に、これからも研究に励んでいこうと思う。